《初心者向け》同人誌通販の完全ガイド|販売までの流れや種類を解説

しまうま出版デザイナーより
「同人誌を作ってみたけれど、どうやって販売すればいいんだろう?」
初めて同人誌を販売する人にとって、通販や即売会の仕組みは少し複雑に感じるかもしれません。この記事では、同人誌通販(ネット販売)の方法を中心に、基本から通販の種類、価格設定や集客方法まで、初心者でも分かりやすく解説します。


はい!自分に合った方法や注意点がわかれば、簡単に販売することができますよ。はじめての方でもわかりやすいようにご紹介しますね!
同人誌販売とは?|通販と即売会の違い
同人誌販売とは、個人やサークルが制作した同人誌を読者に販売することを指します。販売の場は大きく分けて「通販」と「即売会」の2種類があります。
同人誌通販
同人誌通販とは、個人やグループで制作した同人誌をインターネットを通じて販売する方法のことを指します。読者は全国どこからでも購入でき、作り手にとっても交通費やイベント準備の負担が少ないのがメリットです。
同人誌即売会
即売会はコミックマーケットやコミティアのようなイベントで、作り手が直接スペースに立ち、来場者に頒布する方法です。読者と顔を合わせて交流できるのが大きな魅力で、作品への反応をリアルタイムに感じられるのが大きな魅力です。
一方で、当日の搬入・設営・接客など体力的な負担もあり、在庫を余らせてしまうリスクもあります。イベント特有の熱気や交流を楽しみたい人におすすめの方法です。
この記事では、 同人誌通販での販売方法 を中心に解説します。
同人誌を通販で販売するメリット・デメリット
メリット
通販で同人誌を販売する一番の魅力は、地理的な制限がなくなることです。地方に住んでいて、イベントに来られない読者にも届けられます。さらに在庫を持たずに販売できるサービスも増え、初心者でも気軽に始められます。
デメリット
手数料や送料の分だけ利益が減ったり、直接交流できないぶんモチベーションが下がる人もいます。通販と即売会、それぞれの特徴を理解して自分に合った販売スタイルを選びましょう。
同人誌通販(ネット販売)の種類と選び方

同人誌の“通販”とひと口に言っても、在庫を持つか/誰が発送するか/どこで露出を得るか、で仕組みが分かれます。自分の負担・想定販売数・作品ジャンルに合わせて選ぶのがコツです。
自家通販(直販ストア運営)
自分のショップ(個人サイトや汎用ECサービス等)で直販する方式。
価格・セット内容・同梱特典などの自由度が高く、ファンとの距離も近い一方、基本的に在庫管理・梱包・発送・問い合わせ対応は自分の作業になります。
サービスによっては倉庫に在庫を預けて発送を代行してもらうことも可能です。
また、追加料金を支払うことで“匿名配送”を利用し、個人情報を開示せずに発送することもできます。
受注生産/POD型・在庫レス通販(しまうまマルシェなど)
売れる冊数がわからない方におすすめなのがこちらの方法です。
例えばしまうまマルシェでは、買い手から注文が入ってから冊子が印刷・買い手へ発送されるため、販売者は発送の手間がなく、在庫を抱える必要がありません。
自身のSNSなどで拡散する必要があり、ファン以外への宣伝が難しい場合がありますが、販売の手間を減らしたい人や、少部数でも同人誌販売をしたい人、何冊売れるか分からない初心者におすすめの方法です。
委託販売(書店・専門通販に預けて販売)
専門店に在庫を納品し、店舗や通販サイトで販売してもらう方式です。常連以外にも届きやすく、ランキングや特集での露出も期待できます。
審査や規約があり、手数料と在庫送付のコストは発生します。多めに刷る予定・広く届けたい場合に向きます。
電子書籍販売(デジタル頒布)
データ形式で同人誌を販売する方法です。印刷や在庫管理が不要で、コストをほとんどかけずに頒布できるのが最大のメリットです。
ただし「紙で読みたい」という読者層には届きにくく、印刷版より安価で販売されるケースが多い点も特徴です。小説やイラスト集など、デジタルでも違和感なく読める作品に向いています。
基本的な同人誌通販の流れ4ステップ(印刷〜販売登録〜告知〜発送)
基本的に同人誌を販売するまでには、原稿の準備から印刷、通販登録、告知、発送といった流れがあります。それぞれのステップを具体的に説明します。
1. 原稿作成と印刷
まずは原稿を完成させ、印刷所に入稿します。同人誌作りの最初の大きな山場が原稿作成です。
イラストや漫画、小説などジャンルによって形式は異なりますが、共通して大切なのは 印刷所の入稿規定に沿ったデータを用意することです。
トラブル防止のため、販売する場合はページの最後に奥付を記載することも忘れずに行いましょう。
原稿が完成したら、印刷所を選んで入稿します。オフセット印刷とオンデマンド印刷では仕上がりやコストが違うため、部数や予算に合わせて選ぶのがおすすめです。
初めての場合は少部数対応のオンデマンド印刷から始めると失敗が少なく安心です。

2. 商品登録と表紙・サンプル準備
同人誌が印刷できたら、通販サイトや自家通販ページに商品情報を登録します。
ここで重要なのが 表紙画像やサンプルページの掲載 です。購入者は実際に手に取れないため、表紙のデザインや冒頭数ページのプレビューが購入の決め手になります。
商品説明欄がある場合は、ページ数、サイズ(B5・A5など)、価格、発送方法、注意点(R18の場合の表記など)を丁寧に書くと信頼性が高まります。

3. 販売開始と告知方法
販売をスタートしたら、SNSや個人サイトを使って告知します。
Twitter(X)やpixiv、InstagramなどのSNSはもちろん、通販サイトのランキングやおすすめ欄に載る工夫も効果的です。
特にSNSでは、表紙画像とサンプル数ページをまとめた告知画像を投稿すると注目度が上がります。ハッシュタグ(#同人誌通販、#新刊通知 など)を活用し、発売日や通販リンクをわかりやすく提示することも大切です。

4. 発送と在庫管理
自身で発送が必要な場合は、注文が入ったら梱包と発送の準備をします。
梱包は折れや水濡れを防ぐために、クリアパックや封筒、緩衝材を用いるのが一般的です。通販サイトによっては匿名配送や倉庫サービスを利用できるため、個人情報を守りたい人や発送作業に時間をかけたくない人に便利です。
在庫管理も重要なポイントです。手元に在庫を置く場合は数を把握して、通販サイトの在庫数と一致させましょう。在庫切れや発送遅延は購入者の信頼を失う原因になります。
再版の予定がある場合は、在庫が少なくなった時点で事前に告知しておくと「欲しい人を逃さない」販売につながります。


しまうまマルシェでは冊子印刷や発送、在庫管理を自身でする必要がなく、原稿を作成して冊子データを販売登録するだけで簡単に冊子販売が開始できます。詳しい手順や特徴は以下からご確認ください。
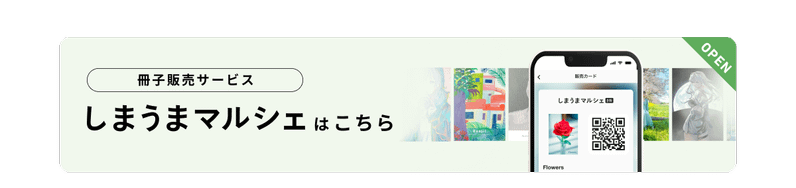
同人誌販売の価格設定|印刷費・利益・送料を考える
同人誌の価格を決めるときは、冊子原価・通販手数料・送料・利益 の4つを必ず計算に入れる必要があります。赤字にならないように意識しましょう。ただし同人誌は趣味の頒布が前提なので、過度に利益を求めないのがマナーです。周囲の相場を参考にしながら、手に取りやすい価格を意識しましょう。
1. 印刷費など冊子原価を把握する
同人誌の印刷費は、サイズ・ページ数・部数によって大きく変わります。たとえばしまうま出版で印刷する場合は、A5サイズ、フルカラー24ページで1部を印刷すると、冊子原価は540円になります。他の仕様での金額も以下からシュミレーションできますので気になる方は見てみてくださいね◎
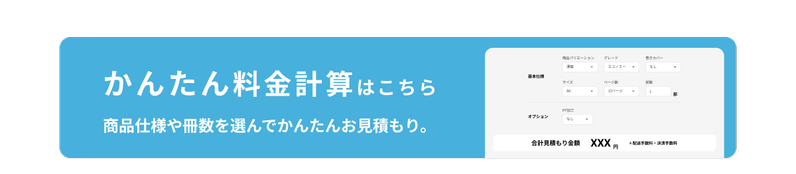
2. 通販の手数料を考慮する
通販サイトを利用する場合は、必ず手数料がかかります。冊子販売のオンラインプラットフォームでは、売上から数%が差し引かれます。委託型通販(書店や専門ショップに置く方式)では、販売価格の三割程度を手数料として支払うのが一般的です。自家通販は手数料0~10%程度ですが、梱包や発送のコストを自分で負担する必要があります。
しまうまマルシェで販売する場合のサービス利用料金は上乗せ額の3%なので、お受け取りいただける金額が大幅に減ってしまうこともありません。そのため、上乗せ額を0円に設定することで、サービス利用料はかからず、購入者に商品原価代と送料だけを負担してもらうことも可能です。
3. 送料を含めた販売価格にする
自身で同人誌を発送する場合の手段としてはクリックポストやゆうパケットポストが一般的で、どちらも200円程です。
また、送料は「購入者に別途負担してもらう方式」と「販売価格に含める方式」の二つがあります。送料別だと商品価格を安く見せられる反面、購入者にとっては合計金額が分かりにくくなります。
一方、送料込みは「買いやすい」という安心感がありますが、その分販売価格がやや高く見えるデメリットもあります。
4. 適正価格の目安
一般的な漫画・小説のモノクロ本なら500〜1000円、フルカラーのイラスト集・写真集なら1000〜2000円程度が目安です。特殊加工を施した豪華本では2000円以上になることも珍しくありません。
最終的には印刷費や手数料、送料をすべて加算したうえで、赤字にならない価格に落とし込むのが理想的です。
同人誌通販の集客方法|SNS・通販ページ・ランキング活用
同人誌を通販で売るとき、一番の課題は「どうやって知ってもらうか」です。集客のポイントは「SNSでの発信」「通販ページの完成度」「ランキングやイベントとの連動」です。
1. SNSでの発信
X(旧Twitter)では、表紙や本文サンプルを画像付きで紹介し、制作過程や通販開始、残部情報などを定期的に発信すると効果的です。
pixivでは作品の一部を投稿して説明文にリンクを添える、Instagramでは表紙やイラストをビジュアル重視で見せる、といった使い分けも有効です。単に一度告知するだけでなく、時間を変えて複数回発信し、異なる層に届くように工夫しましょう。
2. 通販ページの作り込み
自家通販など、販売ページを持つ場合はページ自体の完成度も売上に直結します。自身の情報や、販売冊子の情報を記載するほか、高解像度の表紙画像、数ページの本文サンプル、仕様(サイズ・ページ数・印刷方法・発送予定日)を明記することで、購入者が安心して注文できます。見た目と情報の両面を整えることが大切です。
3. 通販サイト内ランキング・おすすめ枠の活用
通販サイトには「新着順」や「人気順」のランキングがある場合があります。販売開始直後にSNSで一気に告知して注文を集めると、ランキングに入りやすくなります。ランキングに掲載されれば、フォロワー以外の新しい読者の目にも自然に触れやすくなり、販売機会が大きく広がります。
4. イベントとの連動
即売会で本を購入した人が「後で通販でも買おう」と考えることや、即売会で売り切れてしまった場合に見本だけ展示して、後で通販で購入してもらうことはよくあります。
そのため、会場で「通販あり」と告知しておくと効果的です。これにより、イベントに来られなかった人へのフォローができ、在庫消化にもつながります。
同人誌販売・通販でよくある失敗と回避方法

同人誌販売を始める際、多くのクリエイターが直面する共通の失敗が3点あります。事前に確認し、対策していきましょう。
1. 印刷部数の設定
まず、在庫管理の難しさが挙げられます。予想以上に売れてしまった場合、在庫切れになってしまうことがあります。
これを避けるためには、販売開始前に需要を正確に予測し、適切な数の在庫を準備することが重要です。一方、同人誌販売を初めて行う方は数冊単位から印刷を行いましょう。購入者の反応を見て追加印刷を検討すると失敗が少なくなります。
2. 発送トラブル
発送ミスや対応の遅れは購入者からの信頼を失う原因となります。丁寧な梱包と追跡可能な配送を心がけましょう。
梱包時には商品が破損しないよう十分に配慮し、発送スケジュールをしっかりと管理することで、スムーズな配送を心がけましょう。購入者とは迅速で丁寧なコミュニケーションを心がけ、信頼を築くことが大切です。
3. 価格設定が赤字
次に、販売価格の設定ミスです。印刷費や送料を考慮せずに価格を設定すると、想定外に赤字になってしまう可能性があります。
適切な価格設定を行うためには、コストと市場の相場をしっかりと調査し、無理のない価格を設定することが必要です。

3つの失敗は全て、冊子データの登録だけで販売開始できる「しまうまマルシェ」を利用すれば避けることができます。冊子データをしまうまが印刷するだけなので在庫管理はなし、発送もしまうまにお任せ!印刷原価も送料も購入者負担なので赤字になることもありません。
同人誌販売の法律・著作権・R18の注意点
同人誌の販売は多くの人が楽しむ創作活動ですが、法律や著作権の扱い、そしてR18コンテンツに関する注意点を理解しておかないとトラブルにつながる可能性があります。ここでは、同人誌を通販やイベントで販売する際に特に気をつけたいポイントを解説します。
二次創作と著作権の関係
現在の同人誌の大半は二次創作、つまり既存のアニメや漫画、映画などをもとに作られています。オリジナル作品と比べて始めやすく、同じキャラクターや世界観を好きな人と繋がれるため人気ですが、その一方で著作権の問題が常に関わってきます。
作品ごとに権利者の考え方は異なります。ある作品では「SNSでのファンアート投稿は自由だが販売は禁止」とされている場合もあれば、「二次創作は黙認」としている場合もあります。また近年は公式が「二次創作ガイドライン」を公開し、ルールを守れば販売も可能とするケースも増えています。
大切なのは、必ず最新のガイドラインや権利者の意向を確認することです。自分の好きな作品であるほど、原作への敬意を持ち、イメージを傷つけるような表現や営利目的と見られる行為は避けるべきでしょう。
営利目的とマナーの線引き
同人誌は「趣味の創作活動」として広まった文化であり、営利目的と見なされないことが暗黙の前提とされています。たとえ赤字であっても「販売」という形を取る以上、価格設定が高すぎると営利と判断されるリスクがあります。
多くの作り手は印刷費や送料など制作にかかった実費を回収できる程度の価格を設定しています。周囲の相場を参考にしながら、利益を追い求めすぎない価格設定にすることが安心です。
R18作品を扱う際の注意
同人誌の中には性的な表現を含むR18作品も数多くあります。この場合、販売には年齢制限が必須であり、通販サイトやイベントでも未成年に販売してはいけません。オンライン通販を利用する場合は、サイトごとに定められた年齢確認システムやルールに従う必要があります。
また、印刷所にもコンテンツに関する規約があります。R18作品や過激な表現を含む場合、印刷を断られるケースもあるため、事前に利用規約をよく確認しましょう。
法律を守りつつ、安心して創作を続けるために
二次創作は法的にグレーゾーンにある部分も多いですが、だからこそ制作者側が「リスペクト」と「配慮」を持って取り組むことが求められます。公式のガイドラインを調べ、印刷所や通販サイトの規約を確認し、必要に応じて作品の内容や販売方法を調整することが、安心して同人活動を続けるためのポイントです。
まとめ
同人誌販売は、即売会と通販それぞれにメリットがあり、自分に合ったスタイルを選べます。通販は種類も多く、今では在庫を持たずに1冊から販売できる仕組みも登場しました。
印刷所や通販サービスをうまく活用し、価格設定や告知を工夫すれば、初心者でも安心して始められます。あなたの「好き」を一冊にまとめて、多くの読者に届けてみませんか?

最近、同人誌販売が気になっているのですが、初心者なのでハードルが高くて…。自分でもできるでしょうか?